第65回情報・資料研究部会会合報告
内 容
第65回部会はオンラインにて開催された。初参加者を含む全員の自己紹介の後、前半では「第39回全国美術館会議学芸員研修会」の報告書作成に関し、学芸員研修会発表者を交え、実施事項及びスケジュールについて協議を行った。後半では、令和7年度以降の活動内容について検討し、最後に部会員からの情報共有が行われた。
1 「第39回全国美術館会議学芸員研修会」報告書の作成について
(1) 研修会動画のアーカイブ配信の中止について
鴨木幹事より、研修会の動画撮影に不備があり、アーカイブ配信の実施を断念した旨の報告があった。配
信を希望する声もあったことから、代替手段として、報告書を例年よりも早期に刊行し、研修会の内容を可
能な限り迅速に全国美術館会議の会員館と共有したいとの展望が示された。
(2) 報告書の発行スケジュールについて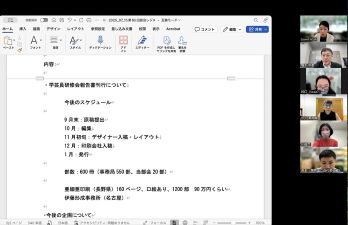
研修会発表者を中心に協議の上、以下のス
ケジュールで進行することとなった。
・ 9月末:原稿提出締切
・ 10月中:編集作業(幹事担当)
・ 11月初旬:デザイナーへの原稿入稿・レイ
アウト作業
・ 12月:印刷会社へのレイアウト入稿
・ 1月:刊行予定
※印刷会社については、今後選定予定。
(3) 報告書の仕様・配布方法
以下のとおり、仕様及び配布方法を検討した。
・ 紙媒体版:600冊(事務局550部、当部会20部ほか)
・ PDF版:全国美術館会議ウェブサイトの会員館向けページに掲載予定
(4) 原稿作成に関する方針
個人発表部分及びパネルディスカッション部分の原稿作成にあたり、以下の方針で進めることとした。
また、SOMPO美術館の西脇芳和館長による開会挨拶の原稿確認については幹事が確認をとることとし
報告書末尾には研修会参加者名簿を掲載する。
【個人発表部分】
・ 音声データの文字起こしをもとに執筆。文体は「ですます」調を原則とする。
・ 原稿の冒頭に発表タイトル、氏名、所属(発表当時の所属を記載し、必要に応じ括弧内に現所属を記載)
を明記する。
・ 文末には、註及び参考文献一覧の付記も可とする。
・ 漢字表記などの統一については原則として執筆者に委ね、必要に応じて提出後に全体調整を行う。
・ 挿図として当日使用したスライドを使用可とし、挿図番号は(図1)、(図2)の形式で記載すること。図版キ
ャプションは別ファイルにて提出すること。
・ 画像データはPPTファイルなどからJPEG形式に変換して提出すること。
・ 画像使用に際し許諾が必要な場合は執筆者が対応する(必要に応じて幹事へ早めに相談のこと)。
【パネルディスカッション部分】
・ 幹事が文字起こしデータをもとに編集した原稿案を
パネリストに共有し、各自が自身の発言部分を校正
する。
・ 他のパネリストの原稿修正により自分の発言部分の
調整が必要になる場合もあるため、上記の校正作業
を1〜2往復行って、最終原稿を完成させる。
2 平成7年度及びそれ以降の情報・資料研究部会の活動
方針について
部会員より、以下のような多様な提案・要望、補足情報
が寄せられた。(以下、各意見の箇条書き+補足説明)
・ 美術関係アーカイブズ資料所在調査の、今後の継続のためのスキームについて検討したい。また、関連す
る見学会や事例紹介の機会があるとよい。(谷口)
・ ジャパンサーチやSHŪZŌなど、横断的なプラットフォームの現状について理解を深めたい。関係者を招い
て話を聞くような会を開催できれば有意義ではないか。(清原)
→鴨木幹事より、この提案に関連して、学芸員研修会のテーマをさらに発展させ、事例報告会、お悩み相
談会のような形式で実施することも有効ではないかとの意見が出された。
→また、奈良県立美術館の事例に関心が寄せられ、同館の三浦氏より、SHŪZŌへの参加状況や画像デ
ータ作成に関する課題について補足説明があった。
・ 作品画像のデジタル化、撮影などにおける注意点や品質基準についてなど、以前学芸員研修会のテーマ
案として提出されたが不採用となったテーマについて、改めて再検討してみてはどうか。(石黒)
→この提案に関連し、川口幹事より、
文化庁が作成した『はじめて取り組むあなたのために-ミュージアムDX実践ガイド』が補足資料とし
て紹介された。
議論の結果、この資料をベースとした勉強会(読書会形式に近いかたち)の実施が提案され、賛同が
得られた。
・ ニュースレター、紀要などに掲載された美術館の研究成果について、単にウェブ上で公開するだけでは検
索・活用が困難である。各館がどのような方法で対応しているのか、また、記事を全文掲載できるような
プラットフォームや機関リポジトリについても関心がある。(山梨部会長)
→この意見に関連して、本報告者(谷口)より刊行物に掲載されない美術館の「研究データ」について、機
関リポジトリを備えていない館が多数であるという現状をふまえ、どのように発信していくべきかにつ
いても検討が必要であるとの意見が出された。
→また、機関リポジトリを導入している東京国立近代美術館の事例について、長名氏より紹介があった。
・ 情報・資料研究部会で開始した活動(美術関係アーカイブズ資料所在調査など)の継続性を担保する手
段として、他機関との連携が選択肢になり得る。以前、山梨部会長が言及されていた東京文化財研究所
(東文研)との連携について、現状の進展があれば知りたい。(長名)
→この意見に対し山梨部会長より、東文研は展示スペースを持たないことから全美に参加できず、これ
まで連携が難しかった経緯が説明された。今後、『日本美術年鑑』における展覧会カタログ掲載文献情
報の採録などについて、全美参加館と東文研が連携することで、より広い範囲の文献が採録可能にな
るのではないかとの見解が示され、連携のあり方について今後の検討事項として取り上げたい旨の発
言があった。
3 その他共有事項
・ 中平氏より、ちひろ美術館では草稿や書簡などの資料整理を進めており、いわさきちひろの言葉を主軸と
した目録を作成予定であるとの報告があった。
・ 三浦氏より、奈良県立美術館では施設の老朽化に伴い再整備の検討が進められており、その期間中にど
のような活動をウェブ上などで展開するかが課題となっている。情報・資料研究部会の活動事例を参考
にしたい旨の発言があった。
→この報告に対し、川口幹事より、美術館改修に伴い作品の移動が生じる場合、収蔵品システムによる
所在管理が重要であること。システム未導入の場合、場所に番号や名称を付して管理する方法も有効
であるとの発言があった。
→また、山梨部会長より関連して、文化庁の「博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推進事業」3次募集に
ついての情報提供があった。
・ 天野氏より、石元泰博フォトセンターの設立10年に際し、アーカイブ書籍の刊行を進めているとの報告が
あった。
4 次回の会合について
第66回部会は、9月下旬ごろに『はじめて取り組むあなたのために-ミュージアムDX実践ガイド』を題材と
した勉強会を実施する予定となった。
1 「第39回全国美術館会議学芸員研修会」報告書の作成について
(1) 研修会動画のアーカイブ配信の中止について
鴨木幹事より、研修会の動画撮影に不備があり、アーカイブ配信の実施を断念した旨の報告があった。配
信を希望する声もあったことから、代替手段として、報告書を例年よりも早期に刊行し、研修会の内容を可
能な限り迅速に全国美術館会議の会員館と共有したいとの展望が示された。
(2) 報告書の発行スケジュールについて
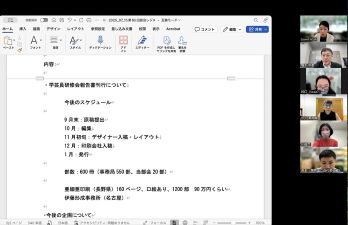
研修会発表者を中心に協議の上、以下のス
ケジュールで進行することとなった。
・ 9月末:原稿提出締切
・ 10月中:編集作業(幹事担当)
・ 11月初旬:デザイナーへの原稿入稿・レイ
アウト作業
・ 12月:印刷会社へのレイアウト入稿
・ 1月:刊行予定
※印刷会社については、今後選定予定。
(3) 報告書の仕様・配布方法
以下のとおり、仕様及び配布方法を検討した。
・ 紙媒体版:600冊(事務局550部、当部会20部ほか)
・ PDF版:全国美術館会議ウェブサイトの会員館向けページに掲載予定
(4) 原稿作成に関する方針
個人発表部分及びパネルディスカッション部分の原稿作成にあたり、以下の方針で進めることとした。
また、SOMPO美術館の西脇芳和館長による開会挨拶の原稿確認については幹事が確認をとることとし
報告書末尾には研修会参加者名簿を掲載する。
【個人発表部分】
・ 音声データの文字起こしをもとに執筆。文体は「ですます」調を原則とする。
・ 原稿の冒頭に発表タイトル、氏名、所属(発表当時の所属を記載し、必要に応じ括弧内に現所属を記載)
を明記する。
・ 文末には、註及び参考文献一覧の付記も可とする。
・ 漢字表記などの統一については原則として執筆者に委ね、必要に応じて提出後に全体調整を行う。
・ 挿図として当日使用したスライドを使用可とし、挿図番号は(図1)、(図2)の形式で記載すること。図版キ
ャプションは別ファイルにて提出すること。
・ 画像データはPPTファイルなどからJPEG形式に変換して提出すること。
・ 画像使用に際し許諾が必要な場合は執筆者が対応する(必要に応じて幹事へ早めに相談のこと)。
【パネルディスカッション部分】
・ 幹事が文字起こしデータをもとに編集した原稿案を

パネリストに共有し、各自が自身の発言部分を校正
する。
・ 他のパネリストの原稿修正により自分の発言部分の
調整が必要になる場合もあるため、上記の校正作業
を1〜2往復行って、最終原稿を完成させる。
2 平成7年度及びそれ以降の情報・資料研究部会の活動
方針について
部会員より、以下のような多様な提案・要望、補足情報
が寄せられた。(以下、各意見の箇条書き+補足説明)
・ 美術関係アーカイブズ資料所在調査の、今後の継続のためのスキームについて検討したい。また、関連す
る見学会や事例紹介の機会があるとよい。(谷口)
・ ジャパンサーチやSHŪZŌなど、横断的なプラットフォームの現状について理解を深めたい。関係者を招い
て話を聞くような会を開催できれば有意義ではないか。(清原)
→鴨木幹事より、この提案に関連して、学芸員研修会のテーマをさらに発展させ、事例報告会、お悩み相
談会のような形式で実施することも有効ではないかとの意見が出された。
→また、奈良県立美術館の事例に関心が寄せられ、同館の三浦氏より、SHŪZŌへの参加状況や画像デ
ータ作成に関する課題について補足説明があった。
・ 作品画像のデジタル化、撮影などにおける注意点や品質基準についてなど、以前学芸員研修会のテーマ
案として提出されたが不採用となったテーマについて、改めて再検討してみてはどうか。(石黒)
→この提案に関連し、川口幹事より、
文化庁が作成した『はじめて取り組むあなたのために-ミュージアムDX実践ガイド』が補足資料とし
て紹介された。
議論の結果、この資料をベースとした勉強会(読書会形式に近いかたち)の実施が提案され、賛同が
得られた。
・ ニュースレター、紀要などに掲載された美術館の研究成果について、単にウェブ上で公開するだけでは検
索・活用が困難である。各館がどのような方法で対応しているのか、また、記事を全文掲載できるような
プラットフォームや機関リポジトリについても関心がある。(山梨部会長)
→この意見に関連して、本報告者(谷口)より刊行物に掲載されない美術館の「研究データ」について、機
関リポジトリを備えていない館が多数であるという現状をふまえ、どのように発信していくべきかにつ
いても検討が必要であるとの意見が出された。
→また、機関リポジトリを導入している東京国立近代美術館の事例について、長名氏より紹介があった。
・ 情報・資料研究部会で開始した活動(美術関係アーカイブズ資料所在調査など)の継続性を担保する手
段として、他機関との連携が選択肢になり得る。以前、山梨部会長が言及されていた東京文化財研究所
(東文研)との連携について、現状の進展があれば知りたい。(長名)
→この意見に対し山梨部会長より、東文研は展示スペースを持たないことから全美に参加できず、これ
まで連携が難しかった経緯が説明された。今後、『日本美術年鑑』における展覧会カタログ掲載文献情
報の採録などについて、全美参加館と東文研が連携することで、より広い範囲の文献が採録可能にな
るのではないかとの見解が示され、連携のあり方について今後の検討事項として取り上げたい旨の発
言があった。
3 その他共有事項
・ 中平氏より、ちひろ美術館では草稿や書簡などの資料整理を進めており、いわさきちひろの言葉を主軸と
した目録を作成予定であるとの報告があった。
・ 三浦氏より、奈良県立美術館では施設の老朽化に伴い再整備の検討が進められており、その期間中にど
のような活動をウェブ上などで展開するかが課題となっている。情報・資料研究部会の活動事例を参考
にしたい旨の発言があった。
→この報告に対し、川口幹事より、美術館改修に伴い作品の移動が生じる場合、収蔵品システムによる
所在管理が重要であること。システム未導入の場合、場所に番号や名称を付して管理する方法も有効
であるとの発言があった。
→また、山梨部会長より関連して、文化庁の「博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推進事業」3次募集に
ついての情報提供があった。
・ 天野氏より、石元泰博フォトセンターの設立10年に際し、アーカイブ書籍の刊行を進めているとの報告が
あった。
4 次回の会合について
第66回部会は、9月下旬ごろに『はじめて取り組むあなたのために-ミュージアムDX実践ガイド』を題材と
した勉強会を実施する予定となった。
(報告者:国立アートリサーチセンター 谷口英理)
参加者:13名(会員名簿順)
山梨絵美子(千葉市美術館)部会長
鴨木年泰(東京富士美術館)幹事
川口雅子(国立アートリサーチセンター)幹事
石黒礼子(国立アートリサーチセンター)
中平洋子(ちひろ美術館・東京)
長名大地(東京国立近代美術館)
廣川晶子(国立工芸館)
三浦敬任(奈良県立美術館)
清原佐知子(大阪中之島美術館)
福田浩子(広島県立美術館)
天野圭悟(高知県立美術館)
折井貴恵(川越市美術館)※学芸員研修会発表者、前半のみ参加
児玉茜(金城学院大学)※学芸員研修会発表者、前半のみ参加
鴨木年泰(東京富士美術館)幹事
川口雅子(国立アートリサーチセンター)幹事
石黒礼子(国立アートリサーチセンター)
中平洋子(ちひろ美術館・東京)
長名大地(東京国立近代美術館)
廣川晶子(国立工芸館)
三浦敬任(奈良県立美術館)
清原佐知子(大阪中之島美術館)
福田浩子(広島県立美術館)
天野圭悟(高知県立美術館)
折井貴恵(川越市美術館)※学芸員研修会発表者、前半のみ参加
児玉茜(金城学院大学)※学芸員研修会発表者、前半のみ参加