第66回情報・資料研究部会会合報告
内 容
第66回部会では、「第39回全国美術館会議学芸員研修会」の報告書編集の進捗と今後のスケジュールについて確認した後、文化庁による『はじめて取り組むあなたのために-ミュージアムDX実践ガイド』を資料とする意見交換を行った。
1. 「第39回全国美術館会議学芸員研修会」報告書の作成について
(1) 報告書編集の進捗及び今後のスケジュールについて
・9月末までに原稿提出済、10月中の編集作業については、有志を募る
・11月初旬:デザイナーへの原稿入稿・レイアウト作業
・12月:印刷会社へのレイアウト入稿
・1月:刊行予定
※当日の発表内容で報告書掲載に差し障りのある部分は掲載を見合わせる方針
※印刷会社については、現在、複数の候補が提案されているが、今後、他の提案も募りつつ、見積もりを
取って選定予定。
(2) 報告書の仕様・配布方法
前回提案のあった以下について、事務局に確認し、方針を決定した。
・紙媒体版:600冊(事務局590部、当部会分10部)
・PDF版:全国美術館会議ウェブサイトの会員館向けページに掲載予定

1. 「第39回全国美術館会議学芸員研修会」報告書の作成について
(1) 報告書編集の進捗及び今後のスケジュールについて
・9月末までに原稿提出済、10月中の編集作業については、有志を募る
・11月初旬:デザイナーへの原稿入稿・レイアウト作業
・12月:印刷会社へのレイアウト入稿
・1月:刊行予定
※当日の発表内容で報告書掲載に差し障りのある部分は掲載を見合わせる方針
※印刷会社については、現在、複数の候補が提案されているが、今後、他の提案も募りつつ、見積もりを
取って選定予定。
(2) 報告書の仕様・配布方法
前回提案のあった以下について、事務局に確認し、方針を決定した。
・紙媒体版:600冊(事務局590部、当部会分10部)
・PDF版:全国美術館会議ウェブサイトの会員館向けページに掲載予定

2. 文化庁による『はじめて取り組むあなたのために-ミュージアムDX実践ガイド』を資料とする意見交換
(司会進行:鴨木)
はじめに、この意見交換の目的として、各館のデジタルアーカイブ化の経験と課題を共有することにあるこ
とを確認(川口)。同ガイドの3つのチャプターのうち、チャプター2「デジタルアーカイブ作成のギモン」チャプ
ター3「デジタルアーカイブ公開のギモン」は個々の館の事情によって対応が異なると予想されるので時間に
余裕があれば議論することとし、チャプター1「DXで博物館はこう変わる」を中心にページに添って協議する
こととした。
(1) チャプター1「はじめに」について
DXという言葉があまり知られていないため、このガイドの対象者が不明瞭(清原)、特にP5の「デジタイ
ゼーション」「デジタライゼーション」「デジタル・トランスフォーメーション」の図で、「デジタル・トランスフォ
ーメーション」の説明として記載のある「サービスの変革」「新しい価値の創造」の意味が曖昧(鴨木)との
意見があった。
(2) チャプター1「変わる01 「望ましい姿」へのトランスフォーメーション」について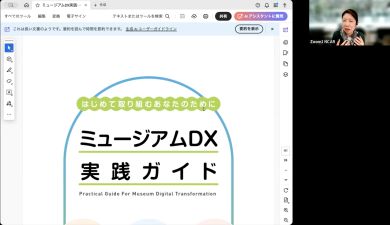
・DXの具体的イメージとして、画像デ
ータベースはデジタライゼーション
で、DXではないという理解でよいか
(中平)との問いに対して、データ
ベース構築だけではデジタライゼ
ーションとは言わず、それによって
学芸業務が効率化され、出退勤、
労務管理などに利用されているの
と同様の効率化が学芸業務におい
てなされていればデジタライゼー
ションなのではないか(鴨木)との
共通理解が得られた。
また、収集委員会資料作成の際、作品管理に候補作品を入力して、そこから書き出すことで業務効率
化ができ、間接的に市民サービスなどにもつながった例(清原)が紹介された。
・このガイドがDXを目標に掲げ、その実現によって現場に利することもある、という流れになっているが、
「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタル・トランスフォーメーション」のどの部分を実現
しようしているかを自覚し、戦略的に取り組む必要がある(鴨木)との発言があり、DXの海外の例とし
て What-is-digital-transformation_JP04.pdfの紹介(川口)があった。
(3) チャプター1「変わる02 どう臨む、どう活かす~別視点からのデジタルアーカイブ」について
・このガイドがDXを目標に現場の所蔵品管理が必要という方向性で書かれているが、現場としては所蔵
品管理から方向づけるという逆のベクトル。「民間の例」に会計システム、労務管理システムなどが挙
げられているが、美術館の具体的業務にどうDXを落とし込むかは簡単ではない。所蔵品データベース
が収蔵庫内の作品と結びついたかたちになっていることが基本となる(鴨木)との指摘があり、公開前
提のデータベースよりも所蔵品管理データの整備が基本(川口)であることが確認された。
・「デジタイゼーション」「デジタライゼ
ーション」「デジタル・トランスフォ
ーメーション」は段階的な構造で、
それぞれに作業・予算を必要とす
るが、その点が設置者側に理解さ
れていない問題(山梨)について
奈良県立美術館ではデジタル化予
算の獲得は出来ず、展覧会予算の
図録作製費によって、出品作品の
カラーポジフィルムのデジタル化
を行っており、文化庁のInnovate
MUSEUM事業三次募集などの助成金を活用し、デジタル化を進めている(三浦)、東京富士美術館で
は、図録作製費にデジタル化費用を組み入れると図録単価が上がる問題があるので、デジタル化予算
は別建て(鴨木)、大原美術館では所蔵品目録のための情報を整理している段階で人手と予算に課題
がある(大塚)などの現状が共有された。
(4) チャプター2「デジタルアーカイブ作成のギモン」、チャプター3「デジタルアーカイブ公開のギモン」につ
いて
・このガイドにはデジタルデータ公開によるリスクの言及が少ない(清原)、ガイドの「ギモン15」「ギモン
16」が公開のリスクについて述べている部分だが、この部分の読み込みが現場としては重要で、ポーラ
美術館では基本的なデジタルアーカイブ化は完了しており、プラスオンする際のリスクに興味がある
(東海林)との指摘があった。
・「ギモン05」のメタデータ作成の最低限必要な項目について、ガイドに記載のあるダブリンコアよりも美
術作品については日本博物館協会のガイド『資料取り扱いの手引き』が参考になる(川口)、デジタル
化とDXの関係についてはユーロピアーナの以下のストラテジーEuropeana Strategy 2020-2025.
pdfが参考になる(谷口)との情報提供があった。
・「ギモン09」「ギモン14」に言及のある国のプラットフォームの活用については、自前での公開が難しい前
提で書かれているが、データ公開の方法として自前での公開についても説明すべきで、①パッケージ・
システムを導入、②クラウドサービスを導入して外部公開、などの例示、ガイドが必要(川口)、それぞ
れの方法や国のプラットフォームシステムのメリット・デメリットなどのガイダンスとともに、そうしたデ
ータ公開と館内業務との関係を解くガイダンスがあればよい(鴨木)との指摘があった。
・作品の基本データ項目のほかに学芸的な業務のデータ項目についてはSpectrum – Collections
Trustが参考になる(川口)、必要なデータ項目や美術館運営上に必要な項目のガイダンスが必要か
(鴨木)との指摘があった。
・「ギモン08」の自館に複数存在する目録データの統合について、当該ガイドでは統合を進めているが、
統合しないメリットもある(鴨木)との指摘があった。
・チャプター2で言及のない来歴・展示履歴情報や各館の刊行物などのデータの活用についての課題
(三浦)については、展覧会図録、年報・紀要などの刊行物の掲載情報も、作品情報の項目として持た
せるのがよい、一方、刊行物の本文をデジタル公開する機関リポジトリについては著作権ほかの権利
関係が課題(川口)との意見があった。
3. 話題共有:特になし
4. 部会長より
本日の内容は参加者のみでの共有は惜しいので、部会として会員館へのデジタルアーカイブのためのガイ
ダンス提供も視野に検討できればと思う。
次回の会合について
第67回部会の日程、内容については、メールにて照会する予定となった。

(司会進行:鴨木)
はじめに、この意見交換の目的として、各館のデジタルアーカイブ化の経験と課題を共有することにあるこ
とを確認(川口)。同ガイドの3つのチャプターのうち、チャプター2「デジタルアーカイブ作成のギモン」チャプ
ター3「デジタルアーカイブ公開のギモン」は個々の館の事情によって対応が異なると予想されるので時間に
余裕があれば議論することとし、チャプター1「DXで博物館はこう変わる」を中心にページに添って協議する
こととした。
(1) チャプター1「はじめに」について
DXという言葉があまり知られていないため、このガイドの対象者が不明瞭(清原)、特にP5の「デジタイ
ゼーション」「デジタライゼーション」「デジタル・トランスフォーメーション」の図で、「デジタル・トランスフォ
ーメーション」の説明として記載のある「サービスの変革」「新しい価値の創造」の意味が曖昧(鴨木)との
意見があった。
(2) チャプター1「変わる01 「望ましい姿」へのトランスフォーメーション」について
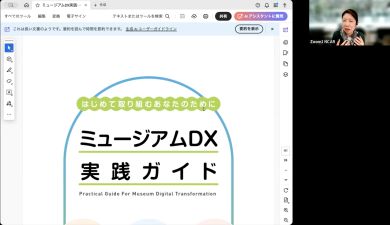
・DXの具体的イメージとして、画像デ
ータベースはデジタライゼーション
で、DXではないという理解でよいか
(中平)との問いに対して、データ
ベース構築だけではデジタライゼ
ーションとは言わず、それによって
学芸業務が効率化され、出退勤、
労務管理などに利用されているの
と同様の効率化が学芸業務におい
てなされていればデジタライゼー
ションなのではないか(鴨木)との
共通理解が得られた。
また、収集委員会資料作成の際、作品管理に候補作品を入力して、そこから書き出すことで業務効率
化ができ、間接的に市民サービスなどにもつながった例(清原)が紹介された。
・このガイドがDXを目標に掲げ、その実現によって現場に利することもある、という流れになっているが、
「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタル・トランスフォーメーション」のどの部分を実現
しようしているかを自覚し、戦略的に取り組む必要がある(鴨木)との発言があり、DXの海外の例とし
て What-is-digital-transformation_JP04.pdfの紹介(川口)があった。
(3) チャプター1「変わる02 どう臨む、どう活かす~別視点からのデジタルアーカイブ」について
・このガイドがDXを目標に現場の所蔵品管理が必要という方向性で書かれているが、現場としては所蔵
品管理から方向づけるという逆のベクトル。「民間の例」に会計システム、労務管理システムなどが挙
げられているが、美術館の具体的業務にどうDXを落とし込むかは簡単ではない。所蔵品データベース
が収蔵庫内の作品と結びついたかたちになっていることが基本となる(鴨木)との指摘があり、公開前
提のデータベースよりも所蔵品管理データの整備が基本(川口)であることが確認された。

・「デジタイゼーション」「デジタライゼ
ーション」「デジタル・トランスフォ
ーメーション」は段階的な構造で、
それぞれに作業・予算を必要とす
るが、その点が設置者側に理解さ
れていない問題(山梨)について
奈良県立美術館ではデジタル化予
算の獲得は出来ず、展覧会予算の
図録作製費によって、出品作品の
カラーポジフィルムのデジタル化
を行っており、文化庁のInnovate
MUSEUM事業三次募集などの助成金を活用し、デジタル化を進めている(三浦)、東京富士美術館で
は、図録作製費にデジタル化費用を組み入れると図録単価が上がる問題があるので、デジタル化予算
は別建て(鴨木)、大原美術館では所蔵品目録のための情報を整理している段階で人手と予算に課題
がある(大塚)などの現状が共有された。
(4) チャプター2「デジタルアーカイブ作成のギモン」、チャプター3「デジタルアーカイブ公開のギモン」につ
いて
・このガイドにはデジタルデータ公開によるリスクの言及が少ない(清原)、ガイドの「ギモン15」「ギモン
16」が公開のリスクについて述べている部分だが、この部分の読み込みが現場としては重要で、ポーラ
美術館では基本的なデジタルアーカイブ化は完了しており、プラスオンする際のリスクに興味がある
(東海林)との指摘があった。
・「ギモン05」のメタデータ作成の最低限必要な項目について、ガイドに記載のあるダブリンコアよりも美
術作品については日本博物館協会のガイド『資料取り扱いの手引き』が参考になる(川口)、デジタル
化とDXの関係についてはユーロピアーナの以下のストラテジーEuropeana Strategy 2020-2025.
pdfが参考になる(谷口)との情報提供があった。
・「ギモン09」「ギモン14」に言及のある国のプラットフォームの活用については、自前での公開が難しい前
提で書かれているが、データ公開の方法として自前での公開についても説明すべきで、①パッケージ・
システムを導入、②クラウドサービスを導入して外部公開、などの例示、ガイドが必要(川口)、それぞ
れの方法や国のプラットフォームシステムのメリット・デメリットなどのガイダンスとともに、そうしたデ
ータ公開と館内業務との関係を解くガイダンスがあればよい(鴨木)との指摘があった。
・作品の基本データ項目のほかに学芸的な業務のデータ項目についてはSpectrum – Collections
Trustが参考になる(川口)、必要なデータ項目や美術館運営上に必要な項目のガイダンスが必要か
(鴨木)との指摘があった。
・「ギモン08」の自館に複数存在する目録データの統合について、当該ガイドでは統合を進めているが、
統合しないメリットもある(鴨木)との指摘があった。
・チャプター2で言及のない来歴・展示履歴情報や各館の刊行物などのデータの活用についての課題
(三浦)については、展覧会図録、年報・紀要などの刊行物の掲載情報も、作品情報の項目として持た
せるのがよい、一方、刊行物の本文をデジタル公開する機関リポジトリについては著作権ほかの権利
関係が課題(川口)との意見があった。
3. 話題共有:特になし
4. 部会長より
本日の内容は参加者のみでの共有は惜しいので、部会として会員館へのデジタルアーカイブのためのガイ
ダンス提供も視野に検討できればと思う。
次回の会合について
第67回部会の日程、内容については、メールにて照会する予定となった。
(報告者:千葉市美術館 山梨絵美子)

参加者:13名(会員名簿順)
山梨絵美子(千葉市美術館)部会長
鴨木年泰(東京富士美術館)幹事
川口雅子(国立アートリサーチセンター)幹事
東海林洋(ポーラ美術館)
石黒礼子(国立アートリサーチセンター)
谷口英理(国立アートリサーチセンター)
伊村靖子(国立新美術館)
中平洋子(ちひろ美術館・東京)
廣川晶子(国立工芸館)
三浦敬任(奈良県立美術館)
清原佐知子(大阪中之島美術館)
大塚優美(大原美術館)
小林豊子(事務局)
鴨木年泰(東京富士美術館)幹事
川口雅子(国立アートリサーチセンター)幹事
東海林洋(ポーラ美術館)
石黒礼子(国立アートリサーチセンター)
谷口英理(国立アートリサーチセンター)
伊村靖子(国立新美術館)
中平洋子(ちひろ美術館・東京)
廣川晶子(国立工芸館)
三浦敬任(奈良県立美術館)
清原佐知子(大阪中之島美術館)
大塚優美(大原美術館)
小林豊子(事務局)